2025年8月5日、大阪万博「ジュニアSDGsキャンプ」の体験プログラムで、ありがたいことに講師を務めさせていただく機会がありました。
任期の関係で現地に行くことは叶いませんが、間接的にでも一大イベントに関われたことが、光栄でした。
開催当初(今も?)は賛否両論ありましたが、タイトルの通り「ジュニア」、つまり子ども達に大好きな南アフリカ共和国について、紹介できただけでも私としては大成功です☺
また、恐縮ですが数名の方から「講演内容を教えてほしい!」と要望を頂きましたので、少し補足しながら紹介させていただきます…!
※気合い入れて作成したPPの動画でも是非!音出ますので注意!
1:本日の流れ

冒頭では、「自己紹介 → 南アフリカの紹介 → 課題の話 → 交流タイム → 最後に」と、まずは今日の講演内容の道筋を示しました。どこの授業でも同じですが、ゴールを示すと理解度が変わってきますね。
ファシリテーターの学生が参加者の皆様に聞いていくれたところ、会場には小学生が多いようでした。それを受けて話口調を調整しました。
2:自己紹介(プロフィール)

次に私は、自分の生い立ちを簡単に紹介しました。
山形で生まれ、東京で育ち、都内公立中学校の社会科教師として働いてきたこと。
柔道部の顧問を務めていたので、教室と道場(と言っても、空き教室に畳を敷設)を行き来する日々でした。
趣味は海外旅行と筋トレ、そしてもちろん柔道。
「ただの先生」ではなく「旅好きで体を動かすのが大好きな人間」など”人となり”を知ってもらうことで、話の入口を少し柔らかくしました。
3:自己紹介(現在の活動)

続いて現在の活動についてです。
今はJICA海外協力隊として南アフリカに派遣され、小学校でPCを教えています。時折、放課後や長期休みでは首都で柔道も指導しています。
ここで伝えたかったのは、「外国人が自国の為に貢献しようとしている姿勢や、日本で培った経験は大小関係なく、海を越えても必ず役に立つ」ということ。私自身がその実例として示したいと考えました。
4:南アフリカについて(位置と距離)

そこで、南アフリカについての紹介に入りました。
当たり前ですが、動画や写真を見せると、子どもたちの”食い付き”が変わります。
恐らく日本人の99.9%が縁もゆかりもなく生涯を過ごすであろう「南アフリカ共和国」に対し、ほんの少しでも親近感を持ってもらうことが狙いです。昔の人が「百聞は一見にしかず」とはよく言ったものですね。何気に温度計の画像への反応が良かったようです。
5:南アフリカについて(首都と言語)

「南アフリカには首都が3つあります」と伝えると、驚きの声が上がりました。
さらに「公用語は12言語。」と付け加えると、会場の空気がざわめきました。(個人的には2023年と最近に”南アフリカ手話”も公用語に加えられたのが、とても素晴らしいと思っています。)
どちらが良い悪いではありませんが、日本人は首都及び公用語は一つと既製概念があると思います。
こう言った話の中で、彼らの「常識」に捕らわれない発想が生まれたのであれば御の字です。
多様性を数字で示すことで、この国の特異な様子を示せた場面でした。
6:南アフリカについて(写真)

さらに魅力的な写真を見せると、子どもたちの表情が変わります。
世代に関わらず動物や食事、きれいな景色は人を引き付ける魅力があります。
年代、人種は違えど、綺麗・可愛い・美味しいは不変です。人間だもの。
7:南アフリカについて(アパルトヘイト)

次に触れたのはアパルトヘイトです。
学校で使える言葉さえ決められ、住む場所も制限され、投票権すら奪われていた時代。
私は「これは遠い昔のことではなく、つい30年前まで続いていた制度です」と念を押しました。
そして、現在の中高年世代は幼少時にアパルトヘイトのもとで過ごしてきたことも伝えました。
美しい写真から一転して、重い歴史を伝えることで印象が深まってくれたら幸いです。
8:南アフリカについて(ネルソン・マンデラ)

アパルトヘイトを語るうえで欠かせないのが、ネルソン・マンデラです。
27年間の獄中生活を経て、なお「白人全般に対する憎しみではなく、将来を見据えた赦(ゆる)し」を掲げた彼の姿を紹介しました。「私ならどうだろう?」と自分に問いかけさせながら、彼の言葉
――「赦しの心は、憎しみよりも強い」――
を子どもたちに紹介しました。憎しみでは同族の一時的な結束は高まっても、共存の道からは逆行します。彼の言葉に歴史の中に生きた“人間の強さ”を感じてほしかったからです。
9:南アフリカの課題(導入)


歴史の話を終えたあと、「では、今の南アフリカはどうでしょう」と切り替えました。
実はこれらの写真は、どちらも同じ地域です。上はヨハネスブルグの中心地とスラム地域、下のケープタウンも同様です。さらに移民の問題も根深いです。
先人たちの努力により改善の兆しは見えつつあるものの、夜明けはまだ先です。
ここからは「過去の国」ではなく「現在の国」として見てもらう時間にしました。
10:南アフリカの課題(経済格差)


最初に取り上げたのは経済格差。南アフリカの現状を語るにあたり、残念ながら外せないテーマです。
世界で最も差が大きい国だとされていることを、グラフで示しました。
子どもたちは、棒グラフの“飛び抜けた数値”に驚いていたようでした。
「この差が、教育や仕事、生活すべてに影響しているんだよ」と補足しながら、格差の重みを実感してもらいました。ですが、まだ子どもたちからしたら直接関係のない”外国”の話です。
11:南アフリカの課題(問題提起)

ただデータを並べるだけでなく、ここで一歩立ち止まりました。
「こんなに差があると、どんな問題が起きると思う?」
問いかけることで、聞き手が自分なりに考える時間を作りました。静かに考える表情が並んでいたのが印象的でした。他者の失敗を自己の正義の為に批判するのは、容易かつ幼稚です。ですが、ともに失敗を乗り越え、自分事としても考えることが社会的動物としての成長につながると伝えました。
12:南アフリカの課題(治安)

次に紹介したのは治安について。
再生数稼ぎのYouTuberがサムネイルに書きがちな文言を一意見として紹介しました。
「犯罪遭遇率150%」という表現に、ざわめきが広がりました。
もちろんただ怖がらせたいわけではありません。
「背景には貧困や失業、歴史がある。だから治安の問題は社会全体の課題なんだ。日本も今後、もしかしたら例外では無くなるかもしれない。」と伝えました。
数字の衝撃をきっかけに、根本原因へと意識を向けてもらう工夫をしました。
そして、ここまでで見てきた格差や治安の問題を整理しました。
「南アフリカの課題は、一つではなく複数が絡み合っている」
その複雑さを理解してもらうことが、この課題パートの狙いでした。

しかし、大切なのは再生数稼ぎの発信者同様に「南アフリカって怖いねー。」で終わらせるのではなく、皆さんと同じように南アフリカにも将来があること。
繰り返しになりますが、ともに失敗を乗り越え、自分事としても考えることが社会的動物としての成長につながると再度、日本の”将来の世代”へ伝えました。
13:交流・質問タイム(問いかけ)


ここからは対話の時間です。
「アパルトヘイトの話を聞いてどう思った?」
「見た目や生まれでチャンスが変わるのは正しいと思う?」
子どもたちの表情からは、ただ受け身の知識を得るだけでなく”自分事として”「考え始めた」様子が感じ取れました。
「世界で困っている人のことを知るのは大切?」
「自分に世界を少し変える力があると思う?」
ここでは本講演全体のメインテーマであるSDGsの本質に踏み込む質問を投げました。
問いかけに多くの子ども達が時間いっぱい反応してくれ、その瞬間「伝わっている」と感じました。




14:交流・質問タイム(自由質問)

「普段何を食べているの?」
「なんで国境は直線なの?」
「緑色の服は制服?」
時間いっぱい、子どもらしい素直な質問に答えながら、場は柔らかく和みました。
重いテーマを扱ったあとの、ちょうど良いクールダウンにもなりました。
15:最後に

締めくくりはシンプルに。
「広い世界が、あなた(の可能性)を待っています!」
知識を持ち帰るだけでなく、「世界に目を向けてみたい」と思ってもらえるように。
この一言に、プレゼン全体のメッセージを込めました。
日本の社会構造は自分や身近な環境の充実、ひいては社会貢献がゴールの一つに挙げられています。しかし、グローバル化が進んだ昨今、その社会という枠組みを日本のみならず世界という視点まで広げて欲しいと願っています。
○まとめ
全体を通して、私は「事実を伝える」だけでなく、「その事実をどう感じ、どう未来につなげるか」を意識して話しました。
南アフリカの話をきっかけに、子どもたちの視線が少しでも広がれば、それが何よりの成果です。
今後も、現在のJICA海外協力隊員という貴重な経験を自分なりの言葉で伝えられるような機会があれば積極的に取り組んで行こうと思います。お読みいただきありがとうございました。SHARP

○追伸
「2025年度の外務省ODA白書/外務省」にて「万博での国際協力出前講座の紹介」として掲載していただくことになりました☺
外務省のHPを確認するような殊勝な方は、ぜひご覧いただけると幸いです☺

旅ゴリの備忘logをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。
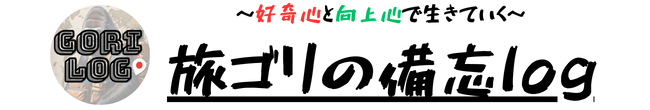



コメント