2025年9月18日(水)に、JICA在外事務所がある首都プレトリアにて「中間報告会」を行いました。
南アフリカでの生活と活動が始まって1年以上が経ち、ようやく自分の立ち位置や役割が少しずつ見えてきました。
この発表を通して、これまでの経験を整理し、「自分はなぜここに来たのか」「これから何をしたいのか」を改めて考えることができました。
初心を忘れない為にも記録しておきます。
⓪目次「自己紹介・配属先紹介・3つの目的・活動のこれから」

順を追って、活動の背景から意義、そして今後の展望までを語る流れにしました。
主題は「中間報告会」とありますが、単なる報告ではなく、これまでの学びとこれからの目標を整理する自分自身にとって大切な節目だと思い行いました。
①自己紹介・配属先紹介


同期隊員からすると今更ですが、お忙しい中、在南アJICA事務所関係者の方も多数参加していただけるとのことでしたので、自己紹介を入れました。
私の配属先はリンポポ州にあるDaniel Mubva Primary Schoolです。
この学校の教育理念は、「教育と生活支援で、子どもも大人も健康で安心して生活できる社会をつくる」こと。
単に授業を行うだけではなく、地域全体の暮らしを支える姿勢が印象的です。
私はこの配属先で、教育現場での経験をもとに、南アフリカの小学校でICT(パソコン教育)を中心に活動しています。
また、放課後には柔道を教え、「教育」と「スポーツ」の両面から地域貢献を目指しています。
ICT教育や柔道を通じて、子どもたちの「未来の選択肢」を広げることが、私の使命でもあります。
②活動の様子

後述する「JICA海外協力隊の3つの目的」を話す前にその目的達成を下支えしている平素の生活について紹介させていただきました。
PCインストラクターとして派遣されたのにもかかわらず、使い物になるPCが無く早々に絶望したこと。
そんななか、「南ア柔道協会」や「Judo for peace」の方々に希望を見出してもらえたこと。
任地での伝統的な生活や子供たちの無償の愛や突拍子もない行動に日々、刺激や感動を貰えていること。 などなど
③JICA海外協力隊の3つの目的
ここからが本題です。
以前、報告書を書いている際に担当のVCから「JICA海外協力隊の3つの目的」を留意して書いてみてはと助言をいただいてから留意して活動しています。
3つの目的は次の通りです。
- 開発途上国の発展への寄与
- 日本と途上国の友好親善と相互理解の深化
- 国際的視野の涵養と経験の社会還元
しかしこれら”3つの目的”は世界中のJICA協力隊員全員に対するものです。
そこで、南アフリカでの現状を鑑み私ごととして、かみ砕いて解釈してみることにしました。

私の配属先である Daniel Mubva Primary School では、ICT教育の導入が行われていませんでした。
使用しているパソコンは教員の私物かつ事務用のみ、電力の不安定さやインターネット接続の問題もあります。
また、教師の多くがパソコンをほとんど使う機会がなく、ICT授業に対して「難しそう」「自分にはできない」という拒否感を持っています。
こうした現状の中で、私は ICT教育の基盤づくり に取り組んでいます。
授業では児童にマウスやキーボードの基本操作を教え、教師にはWord・PowerPointなどの基本的な操作マニュアルの作成を進めています。
また、ICTルームの整備や教材ファイルの共有など、環境面の改善にも努めるつもりです。
これらの活動を通して、少しずつ学校に“変化の芽”が生まれました。
以前はパソコンを敬遠していた教師たちが、ほんの少しですがICTに関する質問をしてくれるようになりました。
子どもたちも「今日はパソコンの日だ!」と嬉しそうに教室へ向かう姿が見られるようになりました。

南アフリカの学校では、日本の文化や教育について触れる機会はありません。
柔道は首都近辺の極めて一部の都市では知られていますが、地方では「カラテ」「カンフー」などの戦うアジアのスポーツという印象が強く、“礼”や“思いやり”といった精神的側面までは伝わっていませんでした。
私は放課後の柔道教室を通して、技術だけでなく日本の心を伝えることを意識しています。
受け身や礼法を学ぶだけでなく、「相手を敬う」「感謝を言葉で伝える」という姿勢を重視しています。
また、授業では折り紙や日本語のあいさつなども取り入れ、
子どもたちが自然と「日本」という国に親しみを持てるよう工夫しています。
活動を続ける中で、子どもたちは「JUDOは戦うことではなく、自分を成長させること」だと理解してくれたのか、少しずつ態度や言葉づかいにも変化が見られるようになりました。

日本では南アフリカについての情報がまだ少なく、多くの人が「遠いサバンナの国」や「治安が悪い国」というイメージを持っています。
しかし、実際に現地で生活してみると、そこには努力を惜しまない教師や、笑顔あふれる子どもたちの姿がありました。
私はそうした現実を日本に伝えるため、ブログやSNSで日々の活動を発信しています。
授業風景、文化の違い、現地の人々との交流などを写真とともに紹介し、「教育の力」や「子どもたちの可能性」をリアルに伝えるよう心がけています。
投稿や交流を通じて、「南アフリカの学校も楽しそうですね」「子どもたちの表情が素敵です」などの反響をいただき、日本と南アをつなぐ小さな架け橋としての役割を感じています。
④活動のこれから
これまでの活動の現状を受け、3月の最終報告会までに行う活動の目標を共有させていただきました。
「中間報告」と「最終報告」はつながっている必要性を感じているのでそのような形にしています。

これからは、ICTを私がいる時のみの特別授業ではなく、学校の文化として定着させることを目標にしています。
今後は、
- 各教科(算数・理科・社会など)にICTを取り入れた授業案を共同で作成する
- 教員自身が自立してICTを教えられるよう、英語マニュアルを整備する
- マニュアルを他校の教員などにも共有してもらい、地域全体のスキルアップを図る
といった取り組みを進めていきたいと考えています。
これらを実現することで、教師が自信を持ってICTを活用し、児童が「考える」「まとめる」「伝える」力をICTを通して伸ばすことができます。
長期的には、“ICTを活用した教育が南アの学びの文化として地域に根づく”という成果を目指しています。

これからは、柔道と文化交流を学校や地域全体へ広げることを目指します。
具体的には、
- 学校行事(スポーツデーなど)で柔道のデモンストレーションを行い、より多くの児童に体験の場を提供する
- 日本の学校・道場とのオンライン交流を実施し、南アと日本の子どもたちが直接つながる場をつくる
- 柔道を教えられる教師がリンポポなどの地方にも関わる機会を作り、人材育成を進める
これらの取り組みを通じて、校長は「柔道を南アの教育の一部として定着させたい」と言ってくれました。
子どもたちが「日本文化を通して学ぶ喜び」を感じられるとこんな嬉しいことはありません。
また、柔道を通じて南アフリカと日本が定期的に交流を続けることで、相互理解と友情の輪が広がることが期待できます。

これからは、単なる発信にとどまらず、教育的な交流の形へと発展させていきたいと考えています。
今後の取り組みとしては、
- 日本の学校とオンラインで交流授業を行い、子どもたちが互いの国を紹介し合う
- 帰国後には、教育関係者や学生に向けた講演・報告会を実施し、現地の教材や映像を活用してリアルな南アを共有する
- 教育雑誌やウェブメディアへの寄稿を通して、南アの教育現場をより広く発信する
こうした活動によって、日本の教育現場でも国際理解教育の素材として南アの事例が活用され、
子どもたちが世界を身近に感じる機会が増えると期待しています。
同時に、南アフリカの子どもたちも「自分たちの姿が海外に届いている」と実感することで、
誇りと自信を持つきっかけになることを期待しています。
⑤さいごに

南アフリカでの日々は、挑戦と驚きの連続です。
けれど、その一つ一つが自分を成長させ、「教育とは何か」「国際協力とは何か」を深く考えるきっかけを与えてくれています。
この発表を終えたあと、「自分はまだ何も成し遂げていない。しかしきっかけは見えてきている。この大地に立てたことで一歩進めた。」
そんな思いが胸に残りました。
発表時点で残り半年。
夢物語のような目標も立てました。すべては達成できないでしょう。
しかし、目標に向かって動くことで何かを得られ、何かを残せると確信しています。
引き続き頑張りましょう。SHARP
旅ゴリの備忘logをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。
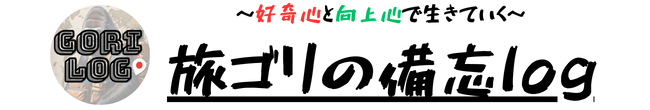



コメント