※真面目回です。アフリカで肉ばっか食べてる内容ではありません※
JICA海外協力隊として南アフリカの小学校に派遣され、早200日を数えた。私はPCインストラクターとしての活動を行っている(つもりだ)が、現地での業務に関して複雑な感情を抱くこともある。
PCインストラクターとしての業務とリソースの現実
そもそも、JICA海外協力隊のPCインストラクターという立場で発展途上国に赴任している以上、限られたリソースの中で活動しなければならないのは当然のことだ。
学校側もPC環境を十分に整備できているわけではなく、私自身もその状況を理解している。指導環境に制約がある中で、できる範囲で子どもたちにPCの基礎を教えることにやりがいを感じることもある。
しかし、だからといって「PCの授業が少ない=暇だろう」と判断され、雑務を次々と押し付けられるのは違うのではないかと感じる。特に、本来は正式にお給料を貰っている教師が行うべき業務の一部を当然のように任されることには抵抗がある。
私たちは+αであり、空いた穴を埋めるピースではないし、他の先生たちの余暇を生み出すために派遣されたわけでもない。
押し付けられる雑務の現状
雑務の中で特に疑問を感じるのは、試験の採点やさらには自習の監督など、いわば「誰でもできる」または「お守り」的な業務だ。そして、責任が伴う。その責任は私には取れない。
確かに、現地の教師たちの忙しさは理解できる。(日本と比べると…だが)
しかし、それが理由で「手が空いている人間にやらせる」という構造ができてしまうと、自分の本来の役割とはかけ離れた業務ばかりをこなすことになりかねない。
それに日本でも同じだったが「できる人がやる」「気が付いた人がやる」では組織としてよろしくない。(日本の公教育の現場では”異動”という仕組みでうまく隠されているが)
特に、課題も出されていない自習監督に関しては「ただ見ているだけ」の時間が長く、教育的な意味でも貢献している実感が持てない。立ち上がる生徒、奇声をあげる生徒をいさめての”もぐらたたき的な指導”の繰り返しだ。
こちらの教師が手一杯、人手不足なのは事実だが、だからといって「PCインストラクターとしての業務が暇なら、代わりに見ていてくれ」と言われると、もやもやした気持ちになる。
積極的に関わりたい業務もある
一方で、すべての雑務が嫌というわけではない。例えば、運動会の手伝いや、柔道教室の開催など、子どもたちと有意義に関わることができる活動には積極的に参加したいと考えている。これは、日本での教員経験や自分の興味にも合致するため、むしろ歓迎したい業務だ。
運動会では、子どもたちが全力で競技に取り組む姿を見ることができたし、現地の文化を肌で感じることができた。柔道教室に関しても、南アフリカの子どもたちに日本の武道文化を伝える貴重な機会となり、私自身のスキルも活かせる。
これらの活動を通じて、子どもたちとの関係を深め、学校コミュニティの一員として認められることにも喜びを感じられる。
この葛藤はワガママなのか?
しかし時折、自分が感じるストレスや不満が「ワガママなのではないか?」と思うことがある。日本では教師が多忙を極める一方で、南アフリカでは私のような協力隊員がいることで現地の教師の負担が軽減される部分もあるかもしれない。そう考えると、「少しくらい手伝うのは当然では?」という気持ちが湧いてくる。現に手伝ってもいる。職員室に戻った時に同僚がTikTok見ていた時はぶちのめそうかと思ったが。
しかし、それでも納得できない部分があるのも事実だ。「意義あるお手伝い」と「便利屋扱い」の間には大きな違いがある。
自分の意思で協力したいことと、無条件に押し付けられることを混同されてしまうと、いくら「助け合いの精神」が大切とはいえ、割り切れない気持ちになる。
また、JICAの協力隊員として活動する以上、持続可能な形で現地に貢献することが求められる。ただ雑務をこなすだけでは、任期中の一時的な助けにはなっても、長期的に現地の教育環境を改善することにはつながらない。
本来のPC教育に集中し、現地の教員や生徒にとって本当に価値のある支援を提供することが、私の役割なのではないかと思う。要請書にも同様に書かれている。
異文化理解の限界と期待のズレ
もちろん文化的な違いを理解する努力はしている。
南アフリカの価値観や働き方に適応しようと努めてはいるが、それを100%受け入れるのは正直不可能だ。
なぜなら、私は2年足らずしか滞在しない外国人であり、この土地に根を下ろすわけではないからだ。これは当たり前の話だ。
しかし、それを理解しながらも、私自身も相手に対して「同じように異文化を理解しようと努めてほしい」と期待していたのかもしれない。向こうにその義務は無い。こちらは反省として書き留めておく。
自分なりの解決策を模索する
- できる範囲とできない範囲を明確にする
- PC授業の準備や、他の教育的な業務に時間を割きたいことを日々伝え、対応できる(すべき)雑務とそうでないものを整理し共有する。
- 「やりたいこと」と「やりたくないこと」の線引きを伝える
- 例えば、「運動会の手伝いや柔道教室には積極的に参加したいが、自習監督のような業務はJICA海外協力隊としての役割にそぐわない」と説明する。
- 学校側と対話する機会を増やす
- 定期的に思いを伝え、自分の役割と学校側の期待している業務内容の確認を行うことで、曖昧な期待値のズレを減らす。
- 断ることに慣れる
- いきなり全てを拒否するのではなく、少しずつ「できないこと」を明確にし、無理のない範囲で応じるスタンスを作る。
最後に:この経験をどう活かすか
異文化の中で自分がどう振る舞うべきかを考えることは、今後のキャリアにも大きく影響するはずだと考えている。
間もなく30代半ばに差し掛かり、自分の人生の方向性を今一度、明確にすべきタイミングだとも考えている。
最終的には、ここでの経験を生かし、同じように葛藤を抱える人々や現地の人々にとって、有意義なものを残していきたい。
そして、自分自身の価値観と折り合いをつけながら、できる範囲で最善の選択をしていくことが、私にとっての課題であり、成長のチャンスなのだと思う。
残り1年間で「何を残せるか、何が残るか、何が得られるか…。」
引き続き「無理をしないで怠けない」の精神で邁進していく。SHARP
旅ゴリの備忘logをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。
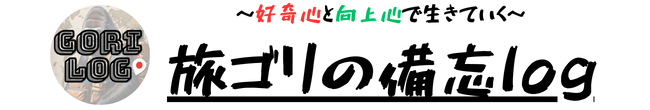



コメント